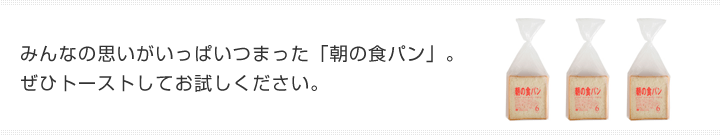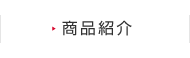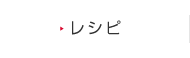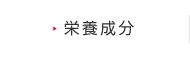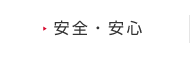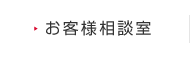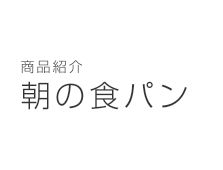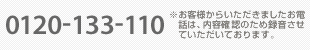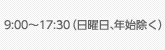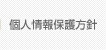こうして試作品ができあがったのですがいざ工場で作ってみると、予想以上に課題が続出しました。
商品になるまでに、何度も何度もテストが行なわれ、根気強く一つ一つ課題を解決していきました。
商品開発担当者だけでなく、工場で働く人みんなのがんばりで力を合わせ、この商品が完成したと言えるでしょう。
3月初旬、岡山工場の食パン係のメンバーに加え、岡山新工場プロジェクトや商品開発、生産技術部のメンバーが見守る中、
『朝の食パン』の工場の中のラインを使ってのはじめての製造テストが行なわれました。
しかし、結果は目を覆いたくなるようなものでした。朝の食パンは非常にデリケートな生地で他のパンでまったく影響のない小さな機械のブレや少しの温度差もすぐに影響をうけてしまったのです。加えて初めて扱う機械もたくさんありました。

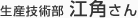
- 江角さんは、岡山工場でラインテストに立会い、岡山工場のメンバーの指導にあたられました。
- 初めての工場で、今まで扱ったことのない機械を使っての新しい商品テストでしたが、何に一番気を付けましたか
- 狙いの商品につなげる生地作りですね。その為に大切なことは、原材料を含めた食材の保管条件や低温醗酵種をいかに安定的にコントロールするかでした。
この低温発酵種の仕上がり具合は、その後の工程や品質を左右する最も大切な仕事でした。 - 起こりえないと思ったこともありましたか
- 工場立ち上げ前に、試作室において100回を越すラボテストをおこない、設置された工程の中で作り上げる製品毎の生地の仕込み条件を作り上げて新岡山工場に入りました。
しかし目の前にしたミキサーの形状を一目見て声が出なかったのが事実です。
同タイプのミキサーでも、仕込量やミキサーの大きさが変われば、生地の出来上がり状態がそれぞれ変わりました。
今までのデータは破棄し、ゼロからの挑戦でした。 - 一番大変だったことは?
- ミキサーの条件を決めるのに、同じ人が同じ視点で24時間つきっきりになって、生地の状態を確認しなければならなかったことでしょうね。
- 今回「朝の食パン」のテストで得たものは?
- 美味しいパンの基本は、以前から「水をしっかり抱き込ませた生地」を「しっかり膨潤させ」そして「しっかり焼きこむ」と伝えられてきましたが、「朝の食パン」はそれを実証した一品です。
今までの発想では、とても完成しなかった商品です。パンの冷却のやり方も含め、いろいろな部分での大きな決断がありました。
また、新しい設備でのレイアウトで、新しい手順や動作が加わりました。
1つ1つの課題を工場の担当メンバーみんなが一丸となって糸口をみつけ、解決したことがノウハウとなったことは大きな収穫です。
ここから、岡山工場において、朝の食パンをつくるための基準作りと日々くり返されるラインテストがはじまったのです。